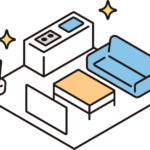区民農園を借りて野菜を作っています。
暑い夏にちょっとへばりながらも、たくさんの夏野菜を収穫することができました。
この夏の野菜栽培と収穫について振り返ります。
それにしても暑い夏でした。
ようやく少しずつ秋を感じるようになってきましたが、まだまだ暑いですし。
前回の報告では、まだまだこれからという感じだった野菜ですが、あれから1ヵ月ほど経って、6月ともなると、かなり大きくなってきました。

この写真は6月半ば頃のキュウリとズッキーニです。
この頃からキュウリは毎日採れるようになりました。キュウリは7本植えたのですが、多い日は7本ぐらい採れる日もありました。毎日3本ほど採れる日が1ヵ月半ほどは続いたと思います。
ズッキーニは栽培が難しかったです。
葉っぱが巨大化して、お隣の敷地に入っていってしまうほどでした。大きい葉は茎から1メートルほどの長さがあったと思います。
実は根本のあたりに付きますが、うまく大きくならなかったり、収穫のタイミングがわからなかったりで、結局、それほどは収穫できませんでした。
本当は、上に伸ばすように支柱を立てて育てればよかったようなのですが、しなかったので、横に横に伸びてしまいました。管理が難しくなって、ある時点で終了としました。

こちらは6月末ごろのミニトマトとピーマンです。
トマトはミニトマトやゴールデントマトなど数種を植えました。最初はなかなか色がつかずに苦労しました。そうこうしているうちに7月、8月の暑さでほとんど実がならなくなってしまい。8月末ごろにすべて枯れました。収穫量はあまりなかった印象です。ただ、ゴールデントマトはかなり美味しかったです。
ピーマンは2本しか植えなかったのですが、コンスタントに実がなりました。8月の暑い時期は実が大きくなりませんでした。9月半ばすぎの今でも、1本は元気に実をつけています。長い間、収穫できるのがいいですね。


一番、収穫ができていた頃の写真です。黄色いトマトがゴールデントマトです。これはかなり美味しかったです。
万願寺トウガラシも収穫期間が長いです。6月半ばの初めての収穫も万願寺トウガラシとピーマンでしたが、9月半ばの今も万願寺トウガラシは毎日のように採れています。
万願寺トウガラシも植えたのは2本だけだったのですが、そのうちの1本は今や2メートル近い高さにまでなって、実もけっこうついています。
ただ、隣の区画の人が手入れをやめてしまったのか、正体不明の草が生い茂っていて、こちらの区画にもどんどん入り込んでいます。この草の影響だと思うのですが、一番近い位置にある万願寺トウガラシとピーマンは弱ってきてしまいました。本当に迷惑な話です。

これは7月末の畑の様子です。
一番手前の畝がナス、真ん中の畝がトマトと万願寺トウガラシ、一番奥の畝がキュウリとピーマンです。左横の区画の人がまったく手入れをしないので、草がボウボウです。
このころはまだ元気だったのですが、8月の暑さでキュウリとトマトはみるみる弱っていきました。

これが9月上旬の状況です。(さきほどとは違う角度からの写真です)
手前に写っている最後まで残った2本のキュウリは枯れ果てました。他のキュウリはこの時点ですでに終了していました。真ん中の畝にあるトマトも見事に枯れました。
ということで、この日にキュウリとトマトはすべて引き抜きました。

これが、キュウリとトマトを引き抜いた後の様子です。
奥にあるお隣の区画の草がすごすぎて、見づらいのですが、ピーマンと万願寺トウガラシはまだ元気にしています。
この夏、初めて野菜作りをしてみました。自分で育てた野菜を食べるというのはいいものです。野菜の味も濃いというか甘いというか、スーパーで買ってくるものよりも美味しい気がするものです。
そして、水やりに毎朝通うというのも早起きの習慣ができて、さらに往復1時間あまりかけて徒歩で通っていたので、健康的にもよかったと思います。
夏野菜の成績
キュウリ :◎ 6月末〜8月上旬にかけて、ほぼ毎日収穫。多い時は7本採れる日も
トマト :△ なかなか色がつかなかった。収穫は7月〜8月上旬ぐらい。
量も多くはなかった
ナス :○ 7月〜9月にかけて収穫。暑い8月は実が大きくならず、皮が固かった
エダマメ :○ 当初植えた4本はほどほどに実がなりおいしかった。
8月に再びタネを蒔いたが育たず
ズッキーニ :× 育て方がよくわからず、あまり実をつけることができなかった
万願寺トウガラシ:◎ 6月半ば〜収穫を継続。暑さのためか実はあまり大きくならない
ピーマン :○ 6月中ば〜収穫を継続。暑さのためか実は大きくならない
さあ、この後は秋冬野菜の栽培へと移行します。
まだ何を作るか決めていませんが、ダイコン、ニンジン、タマネギあたりになるのでしょうか。
来週、目黒区が主催する勉強会があるので、しっかり学んでこようと考えています。
そして、YouTubeの先生たちにも頼ることになるのだと思います。