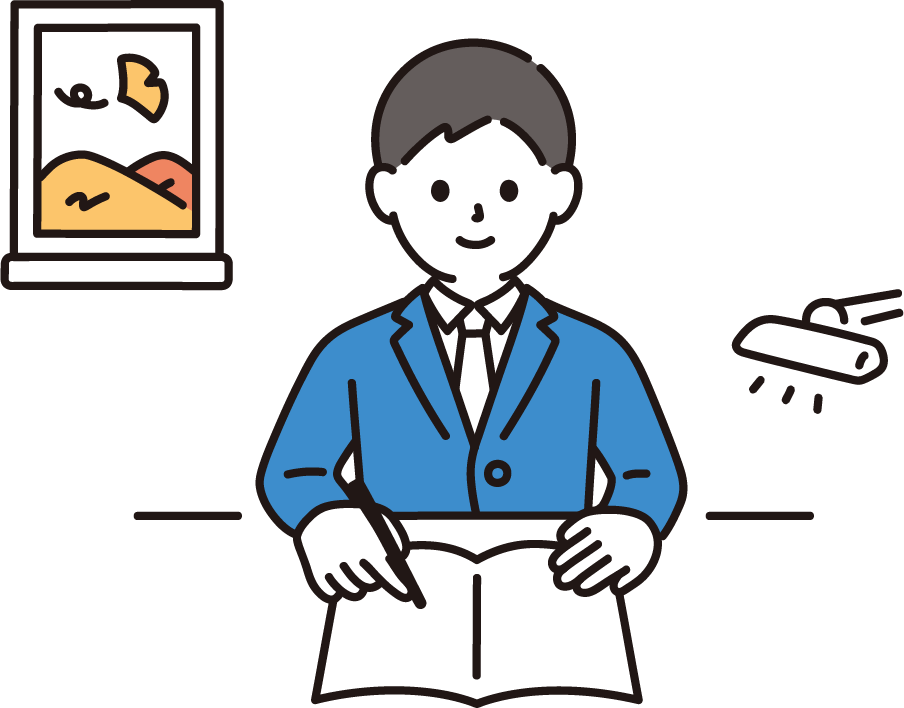おじさんが起業して未経験で不動産会社を始めました。
実際に仕事をしてみて体験した業界の実態です。
今回は相続アドバイザー3級についてです。手強い試験でした。
相続アドバイザーとは
相続○○という資格は世の中に山ほどあります。
そのうち「相続鑑定士」を取得したことについては以前書きました。
→「相続鑑定士になりました」
さらに調べていくと、「相続アドバイザー」という試験があることを知りました。
実はこれ資格というわけではありません。
では何か。
銀行業務検定協会が運営している検定試験です。
要は、金融機関(主に銀行)に勤めている渉外担当者や窓口担当者向けのもので、
基礎知識や実務知識をどれだけ習得しているか測定する検定です。
相続アドバイザーのほかにも、法務、税務、外国為替、年金アドバイザーなどなど
銀行業務に関する検定試験が数多くあります。
→詳しくはこちら「銀行業務検定試験」
その中で相続アドバイザー試験では、相続に関する相談業務に求められる知識の習得程度が
測定されるというわけです。
そしてこの検定試験ですが、金融機関に勤めている人だけでなく、
門戸が広く開かれていて、一般の人も受験できるのです。
3級を受けることに
試験には3級と2級があります。なぜか1級はありません。
そうしたことがわかってきたので、自分の知識がどれほどのものか試してみようと思い、
まずは3級を受けることにしました。
これまで受けてきた3級は、正直「楽勝」でした。
例えば、簿記3級、FP3級(これは正確には受験はしていませんが)、ビジネス会計3級などです。
なので、「相続アドバイザー3級」もすぐに取れるだろうと思っていました。
それが甘かったのです。
内容が想定外の難しさ
テキストと問題集を購入して、勉強を始めました。
すると、とんでもなく細かなことが問われていることがわかりました。
衝撃でした。
問題集を解いてみても、まあ難しいです。
法律の条文の細かなことまで出題されていますし、
そもそも銀行員向けの試験なので、金融実務的なことも問われます。
こちらは銀行の仕事などしたこともないので、さっぱりわかりません。
とはいえ、試験にも申し込んでしまいました。
受けないともったいないので、とにかくやるしかありません。
300ページほどあるテキストをまずは1回読破し、
後は過去問題集を繰り返し解きました。
相続税や遺留分の計算問題もあるのですが、これがまた難しいです。
ひっかけ問題もけっこうあったりして、油断できません。
試験はパソコン方式
試験はCBT方式でした。
ネットで申し込んで、試験日を決め、テストセンターに出向き、
いわゆるパソコンで受験するというスタイルです。
合格ラインは60%以上の正答とされているのですが、
試験直前になってもクリアすることがなかなかできずにいました。
1月下旬、渋谷のテストセンターで受験しました。
全50問。四肢択一式で、試験時間は120分でした。
ちなみに受験料は5,500円でした。
問題は文章が長かったり複雑だったりで、難しいです。
「本当にこれが3級なのか」という実感です。
ほぼ時間を使い切って、試験終了となりました。
CBT方式のいいところといいますか、怖いところは、
試験終了直後に、その場で結果がわかることです。
50問中、正解はいくつあったか‥。
相続アドバイザーは3級でも手強い
なんとか、本当にギリギリでしたけど、合格することができました。
うれしいというよりは、ホッとした感じでした。
相続アドバイザー3級は手強い試験でした。
軽い気持ちで受けるものではありません。
ただこれまで身につけてきた相続に関する知識の確認ができたことは意味がありました。
また資格というわけではないので、名刺に記載するようなものでもありません。
自分の「努力の証」のようなものだと思います。
銀行など金融機関では業務の中で評価の対象になったりするのでしょう。きっと。
相続アドバイザーには2級もあります。
3級でこれだけの難しさですから、2級ともなるとどれだけ難しいのか。
想像すらできません。
受験することは‥、金輪際ないと思います。